 |
 |
 |
こんにちは 遠江病院居宅介護支援事業所です。
日頃よりご協力ご支援ありがとうございます。5月より、新型コロナ感染症は5類に変更とな
りました。皆々様もこれからご活躍の幅が広がって、益々発展されていかれると存じ上げます。
さて、当居宅ではケアマネジャーの仲間と共に風通しの良い事業所として、充実したサービス
とご相談の対応ができる様努めております。
ここで居宅支援事業所の説明をしてまいります。介護相談を頂きましたら居宅契約をして、介
護を必要とするご本人やご家族の希望・要望を盛り込んだ介護サービス計画を作成し、話し合い
をしてサービス利用手続きをします。サービス利用中も利用者様とのコミュニケーションを大切
にして、在宅での生活を快適に過ごしていただけるようトータルサポートしてまいります。
今はいつなんどき災害に巻き込まれるかわからない時代です。新型コロナウイルスの変異も続
くかもしれませんが、24時間皆々様と連絡が通じる体制をとっております。相談を受けましたら
業務継続ガイドラインを作成して、役所、保健所、包括、専門家医療機関をと連携し、利用者の
サービス継続、安全確認を念頭に入れ平時から準備してまいりたいと思います。
私達居宅ケアマネジャーも、より一層研修に参加して自分を研鎖して参ります。また健康維持
のためにこまめな水分補給、栄養、睡眠を十分に取り、お互いに元気でまいりましょう。
いつでもご相談ください。直ぐに対応させて頂きます。お待ちしています。
|
【お問い合わせ】
遠江病院居宅介護支援事業所
浜松市浜北区中瀬3832-1
TEL(053)588-2512
FAX(053)588-2513
管理者: 谷 佐知
|
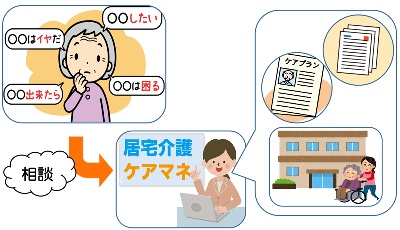 |
| |
| |
|
| メディカル・プロファイリング |
|
死亡率が非常に高い、脳卒中のひとつ
クモ膜下出血(くもまくかしゅっけつ)
クモ膜下出血には、決定的な予防法がありません。
脳ドックや脳神経外科を受診して、脳動脈瘤の大きさや位置、数といったことを
あらかじめ調べておき、脳動脈瘤の破裂リスクに備えることが重要になります。
|
| |
●健康な人にも起こる
脳卒中には、クモ膜下出血のほかに、脳出血や脳梗塞がありますが、クモ膜下出血には、
ほかの二つと大きく異なる特徴があります。
脳出血、脳梗塞は「動脈硬化(血管が硬くなることや血管が詰まること)」が原因で起こるた
め、生活習慣と深い関わりがあります。
対して、クモ膜下出血は、脳を覆うクモ膜とよばれる組織の下の血管にできた「脳動脈瘤が
破裂する」ことで起こります。
この脳動脈瘤がなぜ生成されるのか、はっきりした原因は分かっていません。このため健康的
な生活を送っている人でも、脳動脈瘤がある人は、クモ膜下出血を発症する恐れがあります。
●発症したら至急、救急車を
クモ膜下出血を発症すると、クモ膜下腔に血液がたまり脳を保護している髄膜を刺激します。
このため「金づちで殴られたような」と形容されるほどの激しい痛みとともに、吐き気や意識障
害といった症状が起こります。こうした症状が起きたときは、すぐに救急車を呼びましょう。
これは「警告発作」とよばれるものです。出血量が比較的少なかったことが考えられますが、
重篤なクモ膜下出血が起こる前兆ともいえます。ただちに、医療機関で検査を受けてください。
●破裂リスクを予め知っておく
クモ膜下出血に備えるには、「警告発作」を経験したことのある人はもちろん、そうではない
人も、まず、脳ドックや脳神経外科を受診して定期的に脳の状態(脳動脈瘤の状態)を確認して
おくことが必要です。
ちなみに、クモ膜下出血につながる恐れのある脳動脈瘤は、40歳以上では5%の人にあるとい
うデータがあります。また、クモ膜下出血は、遺伝との関係が指摘されています。血縁関係のあ
る近親者に、クモ膜下出血を経験した人がいる方は注意が必要です。
●経過観察か手術療法
脳動脈瘤を薬物によって治療することは、現在のところできません。このため、脳動脈瘤が見
つかった場合は、瘤の大きさや形の他、様々な条件によって瘤の破裂リスクが検討されます。
瘤が破裂するリスクが低い場合は経過観察を続け、破裂リスクが大きい場合は手術療法が選択
されます。
手術療法には、「開頭クリッピング術」と「血管内治療」があります。前者は、頭蓋骨の一部
を外し、金属製のクリップで脳動脈瘤の根元をはさみ止血を行なうもの。
後者は、股部からカテーテル(細い管)を通し、カテーテルから脳動脈瘤にプラチナなどのコイ
ルを詰めて止血します。
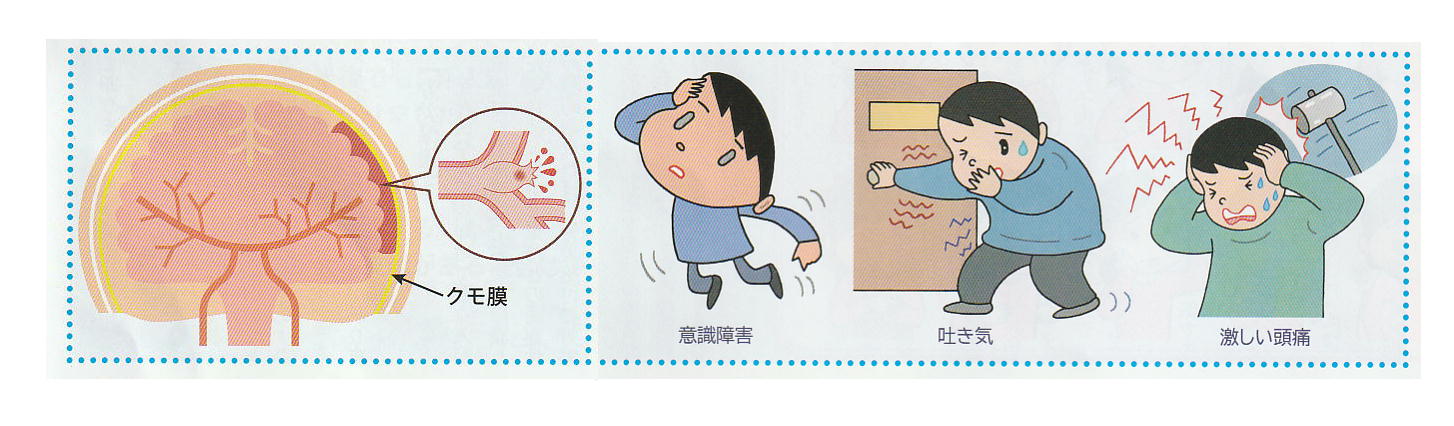

生活ホットニュース ◆◆ 顕著な大雨に関する気象情報 ◆◆
日本では水害による被害が、毎年のように起きています。近年「避難情報に関するガイドライ
ン」が改訂され、「自らの命は自らが守るという意識を持って、自らの判断で避難行動をとる」
との方針が示されました。
そして避難行動の判断のガイドとして、「災害警戒レベル」がお住いの自治体から出されるこ
とになりました(これは、水害以外の災害でも適用されます)。
警戒レベル3では、高齢者はすぐに避難を開始することが必要となっています。警戒レベル4
になると、危険な場所からの避難。災害が想定されている区域では、避難に対しての適格な判断
が求められます。
警戒レベル5は、災害がすでに発生している恐れが極めて高い状況で発令されます。命の危険
が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。
水害の危険を知らせる情報としては、大雨特別警報や洪水警報、高潮や土砂崩れに対する警報
などがあります。また警戒レベル4になると、「顕著な大雨に関する気象情報」が出されます。
この情報は、大雨をもたらす「線状降水帯」が発生すると予測される半日前に発表されます。
顕著な大雨に関する気象情報が出されたら、いつでも避難できるように避難場所や避難経路、
互いの連絡方法を改めて確認しておきましょう。
|
| |
|
| 健康情報誌「こんにちわ」令和5年6月号より(資料提供:メディカル・ライフ教育出版) |

|